花様方言 Vol.192 <戦いと闘いのたたかい>

コロナウイルスとの「闘い」が気になる。「コロナのしゅうそく」は「収束」か「終息」か、という問題は、使い分けているつもりなのか、あるいはただ混乱してるだけか、収束が見えないように思えるが、「コロナとのたたかい」という場合は、少なくともわたくしが目にした限りNHKは100%「闘い」を使っている。戦後の当用漢字世代の年寄りは「たたかう」は「戦う」しか習ってない。だから視聴者からの投稿などには「コロナとの戦い」もあるが、現役のプロの記者が書くような記事では「闘い」でほぼ決まっている。「闘う」と「戦う」はどう違うのか。プロの編集者も使う三省堂『新しい国語表記ハンドブック』には「異字同訓」の用例が載っていて、「戦う」は「敵と戦う」で、「闘う」は「病気と闘う」となっている。なるほどこれでは誰もがコロナとのたたかいは「闘い」だと思う。「闘病」という熟語もある。
当用漢字とは、いずれ漢字が全面撤廃されるのを見込んで、それまでの当座のまにあわせ(当用)ということだ。だから字数も用法も必要最低限に抑えられ、特に訓読みは厳しく制限された。「たたかう」の漢字に2個は要らない、「戦う」ひとつでじゅうぶん、というわけだ。大正時代に流行した「スペイン風邪」のとき「猖獗」(しょうけつ)という言葉が新聞などでよく使われていた。「悪い物事がはびこり、猛威をふるうこと」であり、伝染病の猖獗、コレラが猖獗を極める、のように使う。「猖獗」は当用漢字に選ばれなかった。もうほとんどの日本人はこの字を知らない。が、香港ならかなりの人が知っている。理系の用語でも、梯形→台形、拋物線→放物線、函数→関数、のように当用漢字に書きかえられたが中華圏では今も前者を使う。では、いっそのこと「闘」の字自体をなくしてしまわなかったのは何故か。いくつかの字は日本国憲法に出てくるという理由だけで当用漢字になった。報酬、濫用、威嚇、隷従、奴隷、遵守、詔勅、惨禍、弾劾(それでも濫用は乱用、遵守は順守と書きかえられた)。「闘」も日本国憲法枠(?)での入選かと思って、あらためて全文を読んでみた。憲法の勉強にはなったが、「闘」は見つからなかった。
 「闘」は意外と熟語が多い。闘牛、闘鶏、闘志、闘争、戦闘、乱闘、激闘、死闘、奮闘、拳闘、格闘、そして戦後には、春闘。力道山とアントニオ猪木は、闘魂。これほど生産性があるなら、なるほど、残って当然か。日本の漢字政策はその後、方針が大転換して漢字は廃止されないことになった。漢字はタガがはずれると際限なく増殖するという厄介な性質がある。問題は訓読みだ。三省堂国語表記ハンドブックの異字同訓の用例は「聞く:聴く」「飛ぶ:跳ぶ」「踊る:躍る」「計る:測る:量る」「乾く:渇く」「薫る:香り」など、実に132組にも及ぶ。もはや「闘う」ひとつでおたおた言ってるような状況ではない。
「闘」は意外と熟語が多い。闘牛、闘鶏、闘志、闘争、戦闘、乱闘、激闘、死闘、奮闘、拳闘、格闘、そして戦後には、春闘。力道山とアントニオ猪木は、闘魂。これほど生産性があるなら、なるほど、残って当然か。日本の漢字政策はその後、方針が大転換して漢字は廃止されないことになった。漢字はタガがはずれると際限なく増殖するという厄介な性質がある。問題は訓読みだ。三省堂国語表記ハンドブックの異字同訓の用例は「聞く:聴く」「飛ぶ:跳ぶ」「踊る:躍る」「計る:測る:量る」「乾く:渇く」「薫る:香り」など、実に132組にも及ぶ。もはや「闘う」ひとつでおたおた言ってるような状況ではない。
「戦」には「いくさ」という訓もあるように、本来この字は「戦争(や競争)などで(集団的に)戦う」ことだ。対して「闘」は「対立する二者が闘う」ということだ。コロナとの闘いはウイルスと人類との集団的な「戦い」ではないのか(どこぞの大統領も「これは戦争だ」と言っている)。それに医療従事者や地域住民がコロナと闘うことを「闘病」とは言わない(自分が感染してから「闘病生活」が始まる)。ともあれ、もとより日本語の「たたかう」にそういう区別はない。書き分けには必ずグレーゾーンが生じる。どっちを使ったらいいか迷うし、氷(こおり):凍る(こおる)などは書き分ける必要があるのかと文句を言いたくなる。NHKは字幕で感染者が「200人を越えた」となっていたと謝罪して「超えた」と訂正した。数量や基準を上回るという場合、「超:越」どちらもありとするのが辞書等での一般的解釈だ。が、最近は確かに「超」をイチオシするような説明が目立つ。「200人を越えた」に違和感を覚えるという人たちがすでに一定の割合を越えた(超えた)ということか。「越えた」だと、200人の頭の上を飛び越えた(跳び越えた)ように感じるとでもいうのか。異字同訓の書き分けは増殖の一途をたどる。
現在、「闘」を使っているのは日本だけだ。簡体字では「斗」と書き、香港と台湾の正体字では「鬥」。二人が向かい合って闘っている姿の象形である。だから「対立する二者が闘う」。「門」とは何の関係もない。「闘」が門構えなのは「鬥」の変形にすぎない。西部劇じゃあるまいし、酒場の両開きの扉「門」を開けたら中で決闘、という象形であるはずはない。「鬥」なら、わざわざ余計な「豆寸」を書く手間が省けるのにね。「闘」は日本人の使う漢字のうち、香港の字体より画数が多くなる大変珍しい事例(字例?)のひとつだ。
『鬼滅の刃』は大正時代が舞台の「純和風剣戟奇譚」だそうだが、難読漢字が猖獗していたとはいえ大正は「大正モダン」で、とっても洋風な時代でもあった。スペイン風邪の大流行でカタカナ語「マスク」が普及した。「カチューシャの唄」が流行り、「ライスカレー」を食べ、宝塚や浅草では「レビュー」が、銀座では「カフェー」が大盛況だった(カフェ、ではない)。蕎麦と「サイダー」の取り合わせを好んだ宮沢賢治は妹がスペイン風邪にかかり、それを「インフルエンザ」と、疫学的に正しく書いている。都市には「ビルデング」が建ち、「ラヂヲ」の「アナウンサー」や「タイピスト」「バスガール」など新しい職業が生まれた。「大正デモクラシー」で、「メーデー」も始まった。「デモン」や「デビル」や「サタン」の奇譚が読まれていた時代に『鬼滅』のキャラは「鬼」と戦う。おっと、闘う、か。どっちでもいいだろ。
大沢ぴかぴ






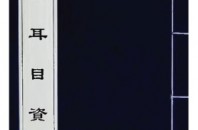




 お得なクーポン満載のPPW公式LINE友だち登録はこちらから!
お得なクーポン満載のPPW公式LINE友だち登録はこちらから! ぽけっとページウィークリーバックナンバー No.908
ぽけっとページウィークリーバックナンバー No.908